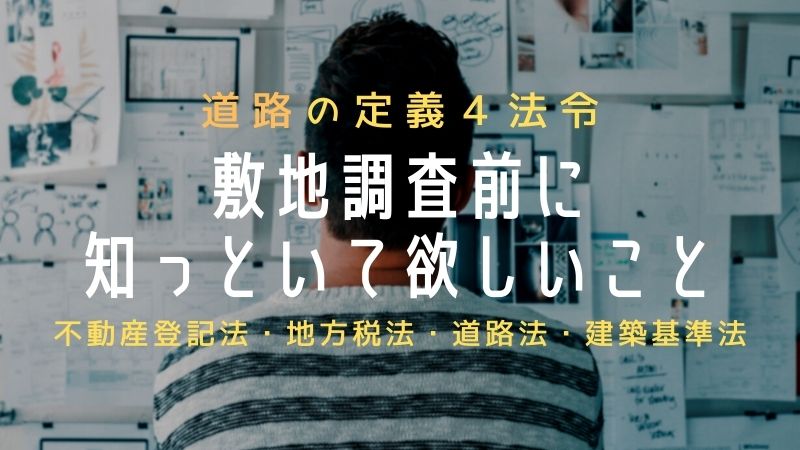- ただ単に「道路」といっても法律によって定義は様々
- 法律&契約の世界では言葉にwell–definedが求められる
自然言語として会話の中で発せられる「道路」という言葉。使う場面と、話し手・聞き手の専門によっては全く意味合いが違うため誤解が生じやすいところです。
重要な言葉は、法令ごとの定義によって一意の解釈または値が割り当てられており(well-defined)、建築計画や不動産売買においては、以下のどの法律の立場から発せられるものなのか共通の認識を持ってコミュニケーションする必要があります。
道路を定義する建築・不動産に関する主な法令は以下の4法令。
- 不動産登記法
- 地方税法
- 道路法
- 建築基準法
※港湾法による道路、道路運送法の道路、土地改良法の農道、公園道・遠路…などは割愛します

建築士と土地家屋調査士と銀行マンなどが入り乱れて地籍調査、融資計画、建築計画をする段階においては、これらの言葉が何法に基づく定義によるものなのかをハッキリさせないと、認識の違いによる手戻りや損害が発生するかも。
そう、法律や不動産売買の世界では、正しい根拠とその内容を正確に伝えることが重要で、文脈から”察する”というのは非常に危険です。
それでは、キーワードごとに整理していきましょう。
「道路」って一言でいうけれど…
まず結論から言うと、道路に関する調査において、建築したい場合は建築基準法、非課税にしたい場合は地方税法、登記したい場合は不動産登記法、認定道路かどうか調べたい場合は道路法、農道について調べたい場合は土地改良法…といった具合に、目的ごとに所管する官公庁の窓口に相談するのがベストです。
| 根拠法令 (所管) | 言葉 | 登記上の 所有 | 管理主体 | 通行権 | 建築のための 接道 |
| 不動産登記法 (法務局) | 公衆用道路 | 官or民 | 官or民 | 誰でも通れるとは限らない | 関係ない |
| 地方税法 (資産税課) | 公共の用に供する道路 | 官or民 | 官or民 | 誰でも通れる | 関係ない |
| 道路法 (道路課) | 高速自動車国道 | 官or民 | 官or民 | 誰でも通れる | できない |
| 一般国道 | 官or民 | 国 | 誰でも通れる | 幅員4m以上ならできる | |
| 都道府県道 | 官or民 | 都道府県 | 誰でも通れる | 幅員4m以上ならできる | |
| 市町村道 | 官or民 | 市町村 | 誰でも通れる | 幅員4m以上ならできる | |
| 建築基準法 (建築指導課) | 1項1号道路 | 官or民 | 国及び地方自治体 | 誰でも通れる | できる |
| 1項2号道路 | 官or民 | 官or民 | 誰でも通れる | できる | |
| 1項3号道路 | 官or民 | 官or民 | 誰でも通れるとは限らない | できる | |
| 1項4号道路 | 基本的に官 | 基本的に官 | 誰でも通れる | できる | |
| 1項5号道路 | 官or民 | 官or民 | 誰でも通れるとは限らない | できる | |
| 2項道路 | 官or民 | 官or民 | 誰でも通れるとは限らない | できる | |
| 法定外 (道路課・ 農村整備課) | 赤道 | 登記なし | 市町村 | 誰でも通れる | 関係ない |
| 青道 | 登記なし | 市町村 | 誰でも通れる | 関係ない |
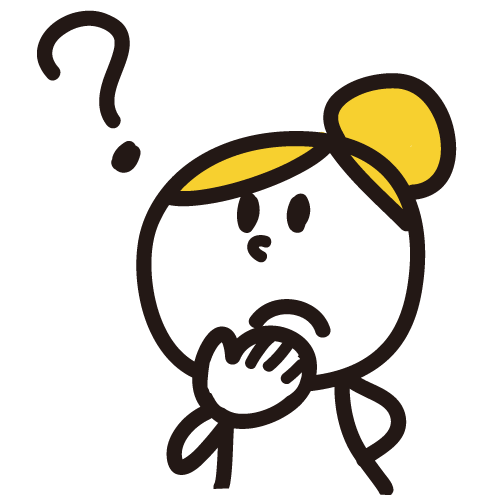
私も表にして気付きましたが、各法令における「道路」ってけっこう民地であることを許容しています。個人の権利が強い日本ですが、法令により少しずつ私権を制限することで、公共の福祉の増進を図っているわけですね…。
「公道」「私道」に法的な定義(一意の解釈)はない
公道・私道という言葉に対して、法令等を根拠とした定義はありません!
よって然るべき場面において公道・私道という言葉を使うことは避けるべきですが、社会通念上は以下の意味で捉えられることが多いと思います。
広義には、道路法上の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、土地改良法上の農道や林道(農林水産省)、河川管理用道路(国土交通省)、自動車道(国土交通省)、法定外公共物(赤線)などを代表として、その”公共性”の視点から語られ、所有or管理が民間であっても不特定多数の人が自由に通行できる場合は公道と呼ばれている。(≒道路交通法の適用範囲)
狭義には”所有者or管理者は誰か”という視点から国・地方公共団体が所有又は管理している場合にそう呼ばれている。(私道の対義語としての公道)
道部分について、不動産登記法による登記簿上の所有者が民間の場合にそう呼ばれている。ただし、以下の点に留意が必要。
- 土地の所有が民間でありながら、市町村により道路認定されると道路法上の道路として自治体が管理をすることになる。
- 自治体への寄付や売買等の経緯があるにもかかわらず登記されていない、いわゆる未登記である可能性もある。
登記の視点から(不動産登記法)
登記の地目「公衆用道路」は現状の土地利用を示しているに過ぎず、固定資産税や通行権、建築の可否とは無関係です!
登記の表題部に地目という項目(フィールド)があります。不動産登記規則99条において地目は21種類が規定されており、その中の1つである「公衆用道路」は、あくまでも現状の土地利用状況を反映させたものに過ぎません。
また、不動産登記事務取扱手続準則68条において「公衆用道路」は『一般交通の用に供する道路』と規定されています。その意味するところは以下の2つのみ。
登記の地目が「公衆用道路」であることの意味
・建築物やその他の工作物が存在しない。
・ある敷地への通行のために使われている。
ところが、公衆用道路という言葉を直感で捉えると、誰でも通行できるとか固定資産税がかからないという発想が生まれてしまいます。が、次の各事項には直接関係ないため注意が必要です。
登記の地目が「公衆用道路」であることと直接関係ないこと
- 課税上の「公共の用に供する道路」であること
- 誰でも通行できること
- 建築基準法の道路であること
- 道路法の道路(自治体による管理)であること
登記上の「公衆用道路」とするメリットとしては、所有権移転登記を行う際の登録免許税の減額です。
具体的には、相続(遺産分割)・売買に係る所有権移転登記について、原則、登録免許税の課税価格を固定資産税評価額の30%とする(=70%引き)ことができたりします。
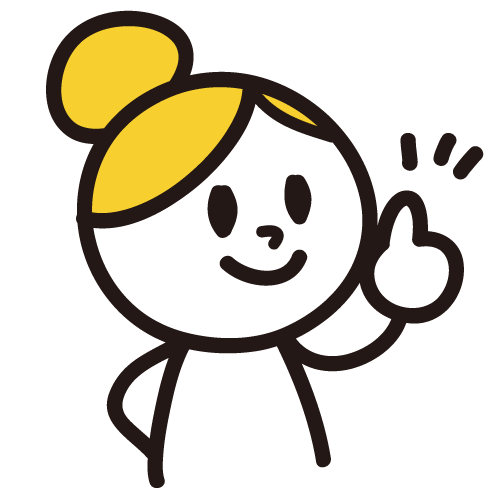
結論としては、登記の地目が「公衆用道路」であっても、何か深い意味あるわけではありません。現状の土地利用状況が「みんなが使える道になっているね」というぐらいの理解でOKです。
税金の視点から(地方税法)
以下の3点が満たされることで地方税法による課税上の「公共の用に供する道路」となり、固定資産税・都市計画税・不動産取得税が非課税となります。
- 開放性:所有者において、何の制約も設けられていないこと
- 公共性:広く不特定多数の人に利用されていること
- 準道路性:道路法にいう道路に準ずると認められるもの(私権の行使が制限されている)
手続きとして、課税上の「公共の用に供する道路」とするには自治体に公衆用道路認定申請(自治体によっては名前が違うかも)を行います。この申請があると自治体の職員が現状を確認したうえで「公共の用に供する道路」として認定します。
なお、以前は分筆登記をしていないと公衆用道路認定申請を受け付けないという扱いがありましたが、最近は分筆登記をしていなくても対象部分が図面で特定できれば受け付けるという傾向にあるようです。
課税上の「公共の用に供する道路」であることの意味
・その土地の固定資産税・都市計画税・不動産取得税が非課税となる。
・私権の行使が制限され、誰でも通れる道路である。
そこで、「誰でも通れて公共性が高いんだから、建築するための接道をとれたり、管理を自治体がしているんじゃないか。」という発想が生まれてしまいますが、次の各事項は直接関係ありません。
課税上の「公共の用に供する道路」であることに直接関係ないこと
- 登記の地目が「公衆用道路」であること
- 建築基準法の道路であること
- 道路法の道路(自治体による管理)であること
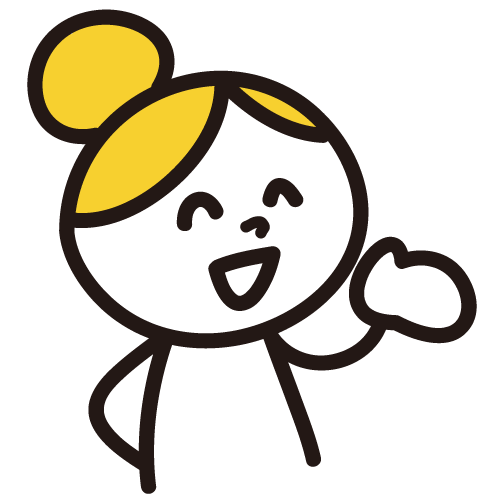
課税上の「公共の用に供する道路」であるかどうかを土地所有者以外が気にすることはありませんが、非課税になっている以上、誰でも通行できることを許容しているということを理解していおけばOKかと。
管理主体の視点から(道路法)
認定道路とは、国又は地方自治体が道路法に基づいて認定を行い、維持管理をしている道路のことです。たとえ”私道”であっても区域内であれば道路法により私権が制限されます。
- 高速自動車国道
- 一般国道
- 都道府県道
- 市町村道
自治体が認定しているものなので、道路台帳と道路網図(地図)をホームページや窓口で閲覧することができます。認定幅員(一般幅員)や路線名も公開しています。
この”認定幅員”は、確認申請書や配置図に記載する「道路幅員」と必ずしも一致しません。建築基準法では、設計者が現況をリサーチし、道路幅員を設定(設計)します。道路法による認定幅員はあくまで目安とするべきです。
さて、建築基準法42条により、認定道路で幅員4m以上のものが建築基準法第42条第1項第一号の道路となり、接道できる道路となることから、道路法と建築基準法は直接関係していると言えるでしょう。
その他、建築関係でいくと看板やオーニングが認定道路の歩道部分にかかる場合などにも道路占用許可をとる必要があるため、道路法(第32条)が関係してきたりします。
道路法の道路であることの意味
・幅員4m以上のものは建築基準法上の道路(1項1号道路)となる。
(幅員4m未満のものは2項道路の要件がない限り基準法上の道路ではない。)
・”私道”であっても私権の行使が制限され、誰でも通れる道路である。
・維持管理を国又は地方自治体が行う。
道路法の道路であることと直接関係ないこと
- 登記の地目が「公衆用道路」であること
- 課税上の「公共の用に供する道路」であること
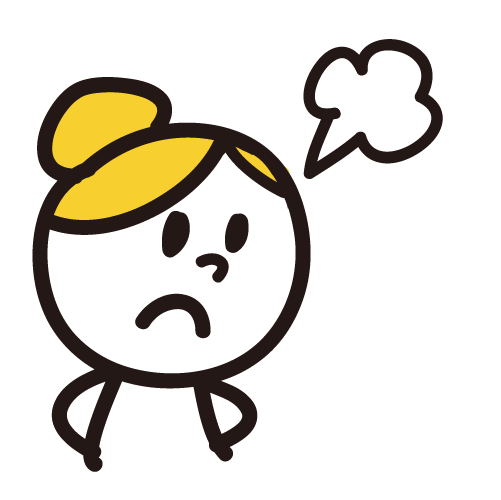
その公共性の高さからか、この道路法の道路であるだけで建築基準法の接道がとれると勘違いする人が結構多いのですよ。県道や市道は自治体が管理している道路である、というくらいの認識でOKです。
建築の視点から(建築基準法)
建築基準法の道路は法42条に定義されており、原則、建築物の敷地はこの道路に2m以上接しなければならないため(法43条)、建築を前提とした不動産売買についてはもっとも重要なトピックです。
建築基準法の道路の判断基準と調べ方については以下の記事へ。
また、建築基準法の道路に接道できないけど建築したい場合の特例許可については以下の記事へ。
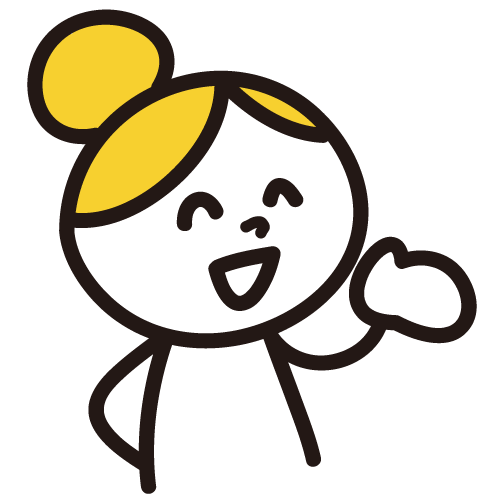
本記事では、建築基準法の道路についての詳細については割愛します。
ご紹介した記事をご参照くださいませ。
管理法の視点から
法定外公共物(赤道、青道)という言葉、聞いたことありますよね。
私たちが普段利用している道路や用排水路、湖沼、池沼などの公共物のうち、道路法、下水道法などの特別法によって管理の方法等が定められているものを法定公共物といいます。
これに対して、道路法や河川法などが適用されないものを法定外公共物といいます。
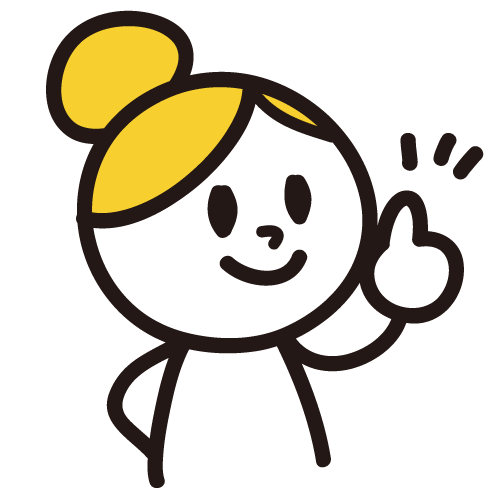
法定外公共物の代表が、里道(赤道)&水路(青道)です。
これまで法定外公共物の所有は国・管理は県となっていましたが、国の地方分権推進計画によって関係法律が改正され、2005年3月31日までに法定外公共物は市町村に譲与されました。よって現在は、所有・管理ともに市町村が行っています。
敷地調査で気を付けなければならないのは、暗渠化もしくは埋められた青道も多くあることです。すでに建築物の敷地に取り込まれてしまい、本来の機能を失った赤道・青道も地域によってはよく見かけます。
「建基法上の道路」と「建築物の敷地」との間に、道路と一体管理をしていない赤道や青道が介在している場合は、特定行政庁や管理課との協議により以下の方法のいずれかで接道を確保する必要があります。
- 占用許可を取って、許可部分を接道とする
- 可能であれば払い下げを受けて自分の土地としてしまう
- 上記2つが無理なら、赤道・青道部分を空地として接道の許可を受ける
敷地内を赤道・青道が横断しちゃっているパターンもよく見かけます。その場合、当然ながら全体を一の敷地とは見れませんので、以下の方法のいずれかの方法により解決します。
- 占用許可を取って、赤道・青道をまたいだ一団の敷地とする
- 可能であれば払い下げを受けて自分の土地としてしまう
- 付け替えを申し出て、公共物の位置を動かす
道路や境界にまつわるトラブルに巻き込まれると大変な目にあいます…。(建築士っぽい仕事じゃないんですよね…。)↓の書籍は建築と境界について分かりやすくまとまってますので、オススメです。
まとめ
色々と書きましたが、私がお伝えしたかったことは、以下の2つ。
目的をはっきりさせて、各法令を所管する行政窓口に直接相談してほしい
「課税上の公共の用に供する道路を確認申請上の敷地に入れると、課税対象になりますか?」は資産税課へ。
赤道・青道の払い下げの協議なら、道路課・農村整備課へ。
建築基準法上の道路かどうかを確認するために建築指導課へ行くのはOKです。
公務員は職務で所管する法令以外のことを責任持ってお答えすることはできません。
たらい回しにあってしまうのは、あなたの知識不足が原因ではないでしょうか。
法律の話をする際には言葉を正しく使ってほしい
敷地調査で「公道ですか?」はやめてください。
「(接道の可否を聞きたくて)公衆用道路ですか?」は質問の主旨が違います。
「(公図を指さしながら)この土地って接道とれますか?」にも答えかねます。
特に不動産営業の方や、銀行の方に多く見られます。断片的な知識を混同してしまって、誰に何を聞いたら良いか分からない方。。
法令の種類と、それぞれに定義される言葉を予習しておくだけで、敷地調査がスムーズにいきますよ。